2025年1月~3月に読んだ本。
あと3冊。
過去の記録はこちら↓。
感想総括
「人生の幸福最大化のために金、健康、経験のトレードオフ最適化をしろ。そのためには『ゼロで死ぬ』を目指せ」と主張する本。
繰り返しが多く正直くどいし、反論はいくらでもあるけど、あえて極端なことを何度も主張して現状に一石を投じているのだと理解している。
少なくともタイトル詐欺ではなく一貫性があるので好感。
日本でも高齢者の預貯金余りが問題になってるらしいし、日本でもこの考え、というか行動が広まればいいんじゃないかな。
高齢者から税金を取る(補助を減らす)のが仕組み上難しい以上、自分から使ってもらうように促す方が国の財政的にも嬉しいのでは?
【追記】
プラチナNISAとかいうのが出てくるっぽいけど、これは正に高齢者の預貯金余りを高額手数料という形で吐き出させる策なのでは?と思った次第。
【印象的なフレーズ】↓
- 「悪い思い出で苦しんで逝く」≪「良い思い出で笑って逝く」
- その時々に相応しい経験をすることが人生の充実度を高める
- やりたいことは今すぐやれ
- 金のことは無意識に重視しがちなので、健康と時間にフォーカスするくらいが丁度よい
- 旅行を躊躇する理由:時間と金(60代未満)、健康(75歳以上)
軽く実践してみた
本書は「資産を無駄に貯めこまず、適宜幸せと交換してゼロで死ぬのが人生の幸せ最大化だ。そのために今できることがあるなら躊躇わずに資産と交換しろ、今やれ」が趣旨だから、本書はホリエモンとか樺沢紫苑型だと感じた。
今やることが無い状態に幸せを感じるボクとは相性が悪いけど、当然得るモノはあるので採用していきたい。
実際、先日の上海旅行で五つ星ホテルにしたのは、本書を読んで「ちょっとは良い体験してみるか」と思ったのが理由。
それが結果的に良い体験だったかどうかは(お風呂入って寝るだけだったから)正直わからない。
ただ、「安宿にしておけばよかった」っていう後悔はしてないから、まぁ良かったんじゃないかな?
トランプのお陰で資産が減っている現在は、ちょっと後悔してるかも(笑)
無職は資産消費計画が立てやすい
ゼロで死ぬための資産計画に関しては、ボクは今後特に稼ぐ当てがないので、本書で言うところの資産のピークは既に迎えているとみなせる。
なので今後減っていく一方なんだけど、逆に考えれば多くの人が踏ん切りがつかないであろう退職(による資産ピークの設定)というビッグイベントを既に迎えているので、在職者よりも計画が立てやすいと好意的に捉えよう。
少なくとも、再就職して苦痛とともにピーク時期を未来にずらすよりは、このまま減る一方でいいかな、と思っている。
ワンチャン、今の状況からでも稼ぎが生まれる可能性もあるわけだし。
実際、これまで年間数十万は稼げてたし(ただし今年はどうだろ?おのれトランプ...!)
“資産を使う”というより”良い思い出を作る”かな
お金と思い出を交換して、思い出配当で幸せバフを得る
本書が自分の人生における資産の使い道を考えるいいきっかけになったのは間違いない。
この考え方は森博嗣の「お金の減らし方(感想)」に通じるものがあると思った。
お金は持ってるだけでは無価値で、欲しいものと交換することで初めて価値が生まれるってやつ。
そんな中で本書の特徴としては、思い出の配当っていう概念。
ボクはこれを漠然と認識はしていたけど言語化したことが無かった(漢字が読めるけど書けない現象)ので、これは本書を読んでよかったポイント。
若いうちにお金と思い出を交換すれば、まるで株の配当金のように、長期間思い出から幸せが得られますよ、だから早くお金を使いましょうって感じで、本書の趣旨を補強させる考え方。
思い出配当には(お金だけじゃなく)人との繋がりも必要?
思い出の配当の概念を知ったので、当然「配当のために思い出を作ろう!」と意気込んでみる。
ただ、経験上、思い出を作るには外部刺激が効果的なんだけど、それは出不精で動画や本ばかり見てるボクに決定的に足りていないもの。
それともちろん、外部刺激を得るためのお金も足りない。
外部刺激の中でも、特に「人との繋がり」が人生における幸せの基礎だよっていうのは他の本(これとかこれとか)でも沢山出てくるので、統計的に「思い出作りが将来の後悔を防ぐ」というのは正しいんだと思う。
なのでお金を使うこともそうだけど、ボクはもっと人と触れ合うことが必要なのかな?
ただ、将来の幸せのためとは言え、それは正直苦痛。
余談:こんなところにも行動経済学
って考えると、「思い出のために生きろ」的な表現に突っ込みを入れたくなってくる(自己正当化)。
これ、本来は「今を全力で生きる→最終的に思い出がいっぱいになる→満足して死ぬことができる」なんだろうけど、それをライフハック的に逆算した結果が「後悔して死にたくなければ思い出を増やす生き方をしろ」という表現になってるんだと思う。
これってある意味ゆがめられてるよな、と。
読者に行動を促すため(幸せになってもらうため)に、行動経済学を駆使してこのような書き方をしてるんだろうけど、ボクはこういうのが気になってしまう。
将来の不幸を人質にして現在の行動を促す脅しじゃん、みたいな
ちなみにこの件で活用されてる行動経済学は、思いつく範囲で以下の3つかと。
- ハロー効果:「思い出」とはつまるところ「主観で印象的な記憶」に過ぎない(≠実際の出来事)
- プロスペクト理論:「思い出を作ること」が「死ぬときの後悔」の回避策になってる
- ピークエンド:終わり良ければ総て良し(極論、過程は無視)
今回のボクの違和感(=順序が逆じゃね?)に直接影響を与えてるのはプロスペクト理論かな。
一人で良い思い出を作る方法
閑話休題。
話を戻して、後悔せずに死ぬには良い思い出を増やす必要があって、思い出には人との関わりが必要ってことだけど、これを疑ってみる。
つまり、人と関わらなくても良い思い出って作れるんじゃね?ということ。
ただ、一人で作れる良い思い出って旅行くらいしか思いつかない。
なのでChatGPTに聞いてみた。
回答は以下。
感性を研ぎ澄ます体験
- 一人旅(とくに自然の中や歴史ある町並み)
- 季節の移ろいを感じる散歩
- 夕暮れや夜明けをじっくり眺める
→ 観察と内省がセットになるので、記憶に残りやすくなります。
創作活動に没頭
- 絵を描く・文章を書く・音楽をつくる
- 手作業のクラフト、模型作り、ガーデニングなど
→ 完成したものが“記憶の物証”になるので、あとから思い出しやすくなります。
「自分との対話」がある時間
- 日記を書く(その日の出来事や気持ちのメモ)
- 本や映画にじっくり向き合って、感想を残す
- 一人での会話を意識的に持つ(心の中での“ひとりごと”でもOKです)
→ 自分の内側に感情の軌跡が残るので、強く記憶に結びつきます。
とのこと。
赤線部が現状のボクに当てはまること。
都合のいいことに、ブログを書くことも思い出に寄与するらしい。
振り返ってみれば、ブログを書く前は(会社勤めだったこともあるけど)漠然と時間が過ぎていくだけだったのに対して、ブログを書くようになってから(退職してから)は日々の出来事をブログに掬い上げて、それに自分の感じたことを加えて言語化しているわけだから、たしかに思い出にはなるよな、と。
ものの本によると、ブログのアウトプットを続けてたらそれがキッカケで人との関わりが発生したみたいな事例もあるらしいので(生存バイアスな気もするけど)、ブログは書き続けようと思う。
その際、人との関わりを目標にしてしまうと書く内容が制限され、それがストレスになりかねないので、「ブログ発信に伴う人との関わり」はあくまでもおまけ(できたらラッキーくらいの気持ち)で、今まで通り思ったこと(=書きたいこと)を正直に書くことを続けていこうと思う。
この方法なら一人で良い思い出を作れるのはもちろん、お金をほとんど使わずに実行できるからね。
まとめ
- 「DIE WITH ZERO」を読んだ
- 趣旨は「お金と思い出、価値があるのは思い出だから若いうちに交換しとけ」と理解した
- これには共感するけど、ボクにはお金が足りない。生活だけでゼロで死にそう(笑)
- お金を使わずに良い思い出が作れたら万事解決では?
- 一人旅やブログ発信でも良い思い出が作れるらしい
- 結論:今の生活を続けよう
以上、
それでは~
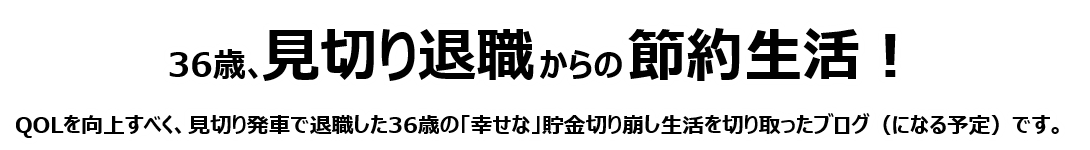
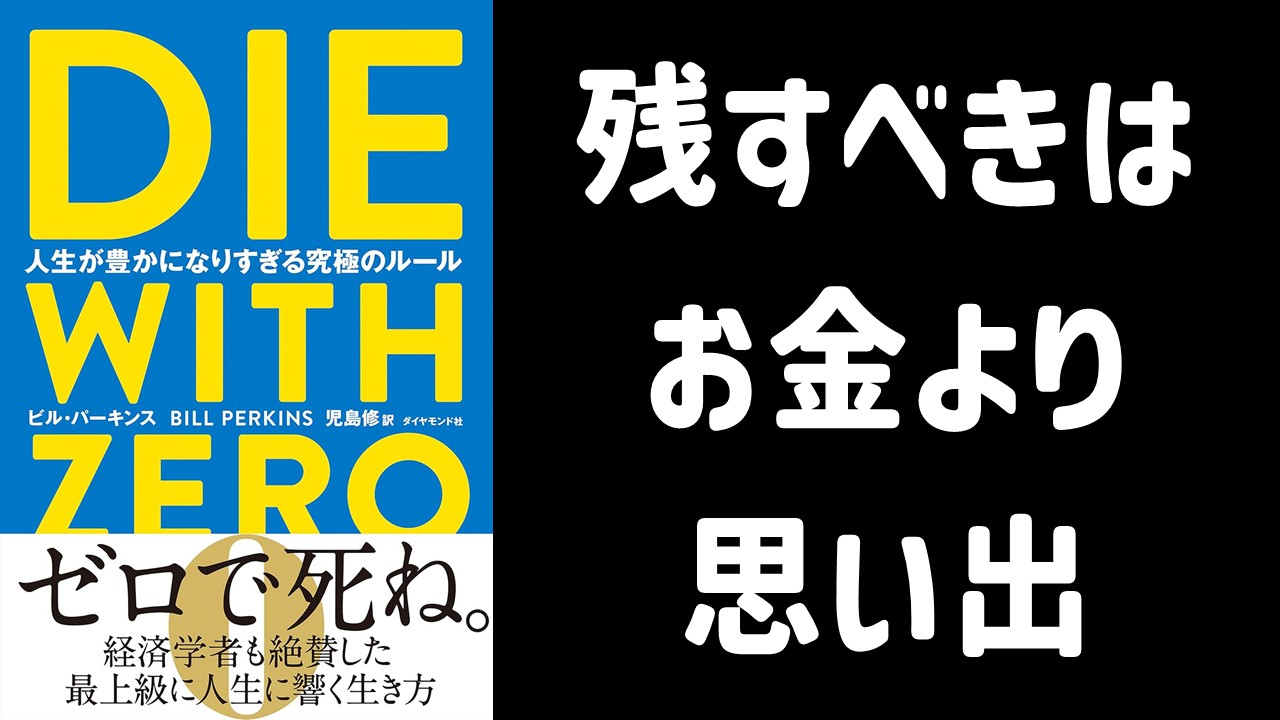


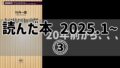
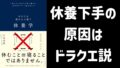
コメント