前回(2024年12月)以降に読んだ本。
あと4冊。
過去の記録はこちら↓。
【竹内一郎】人は見た目が9割
うーん、これはタイトル詐欺
まず思ったのが、20年前からタイトル詐欺って存在していたんだな、って。
冒頭で宣言されているけど、本書における「見た目」とは「言葉以外の情報すべて」のこと。要するにノンバーバルコミュニケーションが9割ですよ、と。本書には音や匂い、温度への言及もあるんだけど、それらも「見た目」ということになる。うーん、これはタイトル詐欺。もっと言えば、20年前から主語でかすぎ問題も存在してたんだな、とも。まぁ「人のコミュニケーションは非言語情報が9割」だと売れ無さそうだもんね。
非言語情報が多い(重要な)のは実感がある
それは棚上げして、ノンバーバルコミュニケーションの占める割合が高いというのは、本書発行後に普及した(と思われる)LINE等のテキストメッセージでスタンプが流行ること等、思い当たる節がありすぎる。以前読んだ「動物たちは何をしゃべっているのか?」でも同じことが逆から書かれていたし(そこでは「言語化が現実の複雑さを切り取ってしまっているのが問題」と書かれていた)。
舞台演出家の視点での非言語情報事例集
本書の内容としては、著者が舞台演出家ということもあり、「人はある感情を持った時にこういう動作をする」ということではなく、「ある動作をした人を見ると、大衆は『この人はこう感じているんだな』と受け取る」ということが主に述べられている。
別の見方をすれば、著者の体験に基づく偏見の嵐って感じ。 2005年の本だから、エビデンスブームの前の本って考えると、まあ納得かな。逆に言うと、偏見でここまで断定してるから面白いっていうのはあると思う。エビデンスを添えたら途端に堅苦しくなって(あるいは都合の良い証拠がないため内容が破綻して)つまらなくなるんじゃないかな。
一番気になった点:「現実に反するけど共通認識になっている演出」問題
読んでて気になったのは、「人間のリアルな反応」と「共通認識になってしまった舞台上での演出」には齟齬がある場合があるということ(例:江戸時代の百姓といえば「ごぜーますだ」と言うに決まっているという共通認識があるが、実際はそんなことない)。
ボクは天の邪鬼だから、フィクションにおける演出のルールがリアルに逆輸入されてしまうことは、リアルがフィクションに侵食されていて良くないという印象を受けてしまう。ある種の洗脳や教育的価値観の刷り込み、といってもいいんじゃないかな?上手い例が挙げられないけど、例えばリアルで死体を見たときに叫び声を上げる人って、どのぐらいいるんだろう?(フィクションでは大体が悲鳴を上げるよね?)
その辺のことに言及してくれたら面白かったんだけど、残念ながらあまり言及されなかった。辛うじて言及されている部分は以下くらいで、
「男は嘘をついた時、目をそらす。やましい気持ちが目に表れる。
p57(太字化したのはボク)
ところが女が嘘をついた時は、相手をじっと見つめて取り繕おうとする。
つまり女がじっと見つめた時は本来怪しいのだが、これはいまだに「世の一般法則」にはなっていない。だから、演技術としても使えない。仕方なく、演出家は、女がやましい時も「目を外す」演技をつけることになる。
ドラマであれば、現実と異なっていても、観客に通じればいい。そこであえて共通の了解事項から離れる必要はない。問題は真実から外れた「一般法則」(人は男女を問わず嘘をつくと目をそらす)が定着しているというところだ。この勘違いから逃れないかぎり、女の嘘を見破るのは難しいということになる。」
「事実と異なる共通認識が普及しちゃうと、事実を見抜くのが困難になるよ」までで言及が止まってしまっている。残念。
事実であろうがなかろうが、それが共通認識だと把握しておけば有利
「事実と異なる共通の了解事項を広めたのは誰か?問題」はたぶん鶏が先か卵が先か問題になって埒が明かないので、起源とか根拠は置いておいて、「『こういう動作に対してはこういう見られ方をする』っていう認識が広がっているから、利用したもん勝ちだよ」ぐらいに捉えておくのがいいと思った。
余談だけど、本書では手塚治虫等の漫画表現にも言及があったけど、漫画界においては上述の「事実と異なる共通の了解事項を広めたのは誰か?問題」の答えは明白で、彼をはじめとした漫画家が広めたのは間違いない。ただ漫画は2次元で、リアルではないことは明らかだから「事実と異なる(=誤解が生じると生活上困ることがある)」っていう表現は適切ではなくて、「便利な(=説明を省略できる)」って表現が適切なのかな。
最後に、本書を読んで、「当事者間で起こっていることを第三者に伝えようとする(=演技する)と確実に違和感が発生する」ということと、「フィクション作家はこの違和感を如何にコントロールするか、が腕の見せ所である」っていうのを改めて感じた。
以上、
それでは~
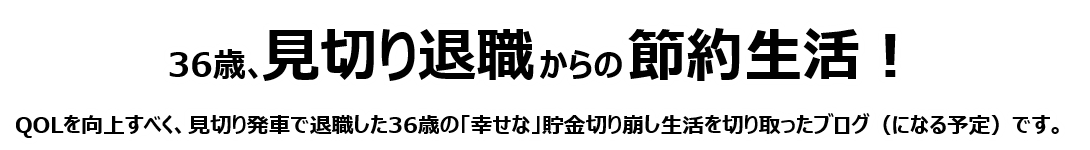
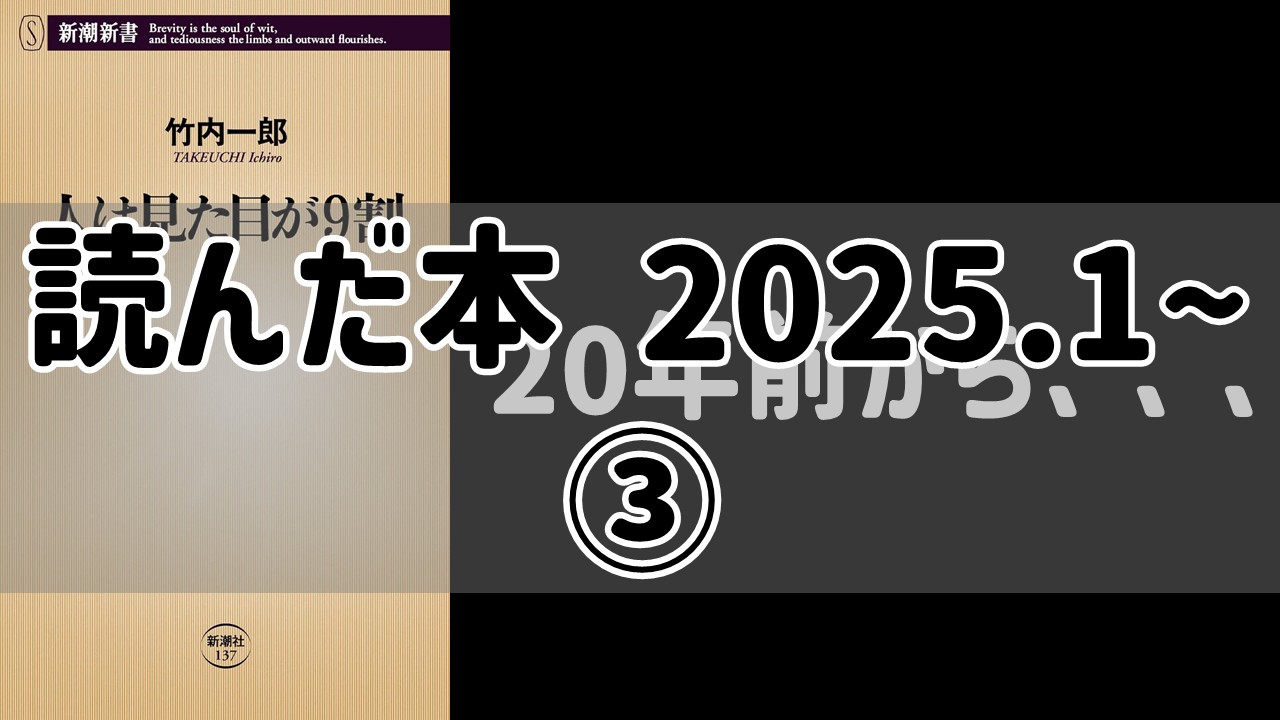


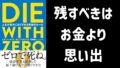
コメント