前回(2024年12月)以降に読んだ本のまとめ。
読んだ本&短文感想。
3月までに読んだ本は、
この記事の分を含めずにあと5冊ある。
過去の記録はこちら↓。
【堀江貴文】最大化の超習慣「堀江式」完全無欠の仕事術
Amazon Prime Readingで読んだ本。
いつものホリエボン。「習慣」を軸にして、著者がいつも言っている内容が整理されている。本人が言っているように、著者の本は同じ本質を希釈して焼き直したものばかりなので、期間を空けて読むといいカンフル剤になる。それなら別に同じ本を読み直しても効果は変わらないんだけど、一度読んだ本を敢えてもう一度読む気にはならないから、定期的に(ほぼ)同じ内容の本を出してくれるのはありがたい。プライムリーディングで実質無料(月500円弱)だしね。
今回カンフル剤になったのは、
- 「楽しそう」と「楽しい」は別物
- 「今」やれ
- 「たくさん」やれ
- 損得なんか考えず、自分に正直になれ
- ストレス回避策①:いずれ辻褄が合わなくなって面倒→嘘をつくな
- ストレス回避策②:過去未来を思うと不安→予定を埋めろ→今に集中せざるを得なくしろ
あたり。
ストレス回避策②以外は正にカンフル剤で、「はいはいそれね、知ってますよ。思い出させてくれてありがとう」といった感じ。ストレス回避策②については、今のボクが毎日暇でダラダラしているのに不安にならないのは何でだろう?と考えるキッカケになった。
可能性としては「ボクに不安の種がある/ない」×「ボクは不安を感じている/いない」の4パターン考えられて、たぶん「不安の種はあるけどそれを不安と感じていない」んじゃないかな?これについては深く考えると不安を掘り出すことになってしまうからここで止めておく。間違いなく言えるのは、今のボクは不安を感じてなくてハッピーということ。
以下、特に気になったフレーズを2つ引用。
本質はあくまでも事後的に発生するものであって、本質という抽象はそれ単独で先行的に存在するものではない。
位置:149
これは参考になったとかではなく、ハンターハンターで世界樹の頂上でジンがゴンに言ったことが正にコレだよな、と思った次第。この言葉からはいろんな教訓が引き出せそうだけど、ひとつ言うなら「行動しなきゃ始まらない」ってことかと。
聞いてるか~>自分
ぼくはぼくの時間のひとつひとつを最大限に使ってきたことをあなたに誇りたいのである。そしてあなたもそうあってほしいと思う。
位置:220
これが本書の中で一番ホリエモンらしい言葉だと感じた。まぁボクが著者の何を知ってるんだ、って話ではあるんだけど。時間を無駄に垂れ流しているボクとは対照的だなぁ、と。以前のボクならこういうのを読むと「時間を垂れ流してる自分はダメだ!」みたいな方向に考えちゃってたんだけど、今ではすっかり「著者はこういう人なのね。素晴らしい。それはそれとして、ボクは時間を垂れ流せる生活を送れていることを誇りたい」と思えるようになっている。ボクも成長(?)したもんだ。
【森博嗣】つむじ風のスープ The cream of the notes 13
年1回のカンフル剤。クリームシリーズ(100個のテーマについて著者が見開きで考えを書くシリーズ)の13冊目。テーマが100個もあって、そのひとつひとつに気付きがあるので、考えること/共感することが多すぎて感想が書けないことで(ボクの中で)有名なシリーズ。とは言え13冊も出しているので、著者の考えの芯となる部分は炙り出されてきた感がある。にもかかわらず面白いのは、考え方だけじゃなくて文章が面白いからなんだよな、と。
「72 洗剤も消臭剤も風邪薬も滋養強壮剤も缶コーヒーもビールもどこまでも良くなる?」は、ボクが常々思っている、詐欺とビジネスの境はどこ?みたいな話で、全文引用したいくらい同意した。
その他刺さった所を引用と共にいくつか適当にピックアップ。
世の中にはいろいろな人がいる。(中略)物理的な害がなければ、問題ない。
位置:248
ボクは著者と違って「死ぬまでに使い切れないお金」を持っていないので、「問題ない」範囲に「金銭的な損失」も含めたい。
核の部分に他者からの借りものを据えると、いくら上手に膨らませても、オリジナリティが感じられないものとなる。オリジナリティがなければ、創作する意味がない、といっても過言ではない。
とはいえ、これは少しいいすぎで、趣味として楽しむ範囲ならば、オリジナリティは必要ない。
位置:442
本書を読んだ「なろう系で生計を立てている人」は、ここを読んでどう思ったんだろう(笑)
もしボクが該当者なら、「なろう系は創作ではない。商業作品だ」って自分を納得させると思う。
あ、そもそも創作を志す人はなろう系を書こうとは思わないか
描かれない時間であっても主要なメンバの重大な出来事は、必ずなんらかの言及があり、思い出などで描かれるという前提、あるいは暗黙の約束があるようだ。僕は、そんな約束をした覚えはないけれど、確実に存在するみたいなのである。
(中略)
(読んでいて)「あれ、変だな」と感じたら、「そうか、どこかで会って、話をしたんだな」と想像する。
(中略)
物語で描かれなくても、そんな陰の時間が流れている、と考える方が自然だ。二次創作などは、ここを補塡しようとしている。
位置:737 ()内はボクが補足
これがボクが森博嗣の小説にリアリティを感じる理由の一端。
現実でも他人の行動や思考を把握するのは不可能だから、「見える範囲の断片情報から推測して会話で確認する」の繰り返しで話が進んでいくものだと思う。なのに小説になった途端、神の視点を手に入れて、登場人物の行動や思考を一本筋が通るように時系列に並べられると違和感が凄い。その違和感が無視できるくらい面白い作品も当然あるけど、ボクは違和感の少ない(=リアリティがある)作品が好きっていう話。
あ、ここから連想したんだけど、ボクがドラクエ3のHD2Dリメイクをイマイチだと感じる理由もコレに関係してそう。プレイ動画を見る限り、リメイクでオルテガ周りの話がやたら追加されてたけど、これはファミコン時代には(容量の都合で?)果たせなかった「すべてのことが描かれる」という暗黙の約束を果たした結果なんだと思う。
でも、ボクにとってはこの追加はただの冗長というか、押しつけに近い何かだと感じてしまった。当時の少年たちがそれぞれ想像で補っていたオルテガの冒険を、リメイクとはいえ公式が一意に確定させてしまったせいで、少年たちの補完した数多のオルテガ像が否定されてしまった、みたいな。小説や漫画の映像化により、それまで個々の脳内にのみ存在していた姿や声が一意に定まってしまった喪失感?もこれと同じことだと思う。
ドラクエ3に関しては、そんなところに容量を使うくらいなら、戦闘時に自キャラを常時表示させることに容量を使ってくれよ、と切実に思った(懐古厨乙)。ロマサガ2リメイクを見習って、どうぞ
突然便利なものを与えられた原始人みたいに見える。ちょっと刺激が強すぎたのではないか。彼らが持っていた文化が消し去られはしないか、まるで麻薬のように常習性があって不健康なのではないか
位置:839
スマホを手放せない人への言及。
この、現状の観察結果を書いただけなのに皮肉っぽくなってる言い回し、シニカルっていうの?エスプリが効いてるっていうの?たまらない。成田悠輔との共通項。そこが大好き。
森博嗣の思考の一端に触れたい。そう望んで、クリームシリーズを手に取っている読者が多いのではないだろうか。もちろん、私自身もそうだ。
玉石混交のインターネットの海から玉をより分けるのではなく、慣れ親しんだ森博嗣節で新たな気付きや知見を得たいのです──。 これは、解説でも感想でもなく、身勝手な願望である。
位置:2668, 2714
これは解説文(≠著者の言葉)からの引用。一番共感した。ボクは無意識に「森博嗣は別格、理解が及ばない人」と認識してしまっているので、「森博嗣の読者」という意味で同じレベルの解説者への共感が強いんだと思う。
刺激には慣れてしまうもので、冒頭に軽く書いたけど、悲しいことに本書の目次100項目を見て、結構な割合でなんとなく話の方向性が予想できてしまった。そしてそれらがあまり外れていないことにショックを受けた。まぁ方向性は当たっていても、考えの深さという点では未だ全然ボクの考えも及ばないところまで書かれているから、まだまだ気づきはあるんだけど。
ただ、その深さ方向もだんだん予想できるようになって、ボクの中に森博嗣エミュレーター?みたいなのができあがってしまった時が、ボクが森博嗣を卒業する時なんだろうな、なんて漠然と考えた。
ところで、方向性が読めてしまって寂しいって思うようになったのはボクがブログを書き始めたことが原因のひとつかもしれない。ブログを書く前は、ただただ読み散らかして内容を右から左に流して、その流れていく間だけ楽しんでいたんだけど、ブログで本の内容に自分の考え(という名のただの内容の劣化コピーかも)を添えてアウトプットすることで、右から左に流すだけじゃなくて多少は吸収できるようになった感じ。ブログに本の感想を書くことで自分の思考力は(たぶん)鍛えられてるけど、代わりに本から得られるものが減っていく。これがトレードオフってやつか。。。
ホリエモンと森博嗣のカンフル剤としての違い
この記事ではたまたまホリエモンと森博嗣の本の感想になった。ボクにとってはどちらの本もカンフル剤と見做しているんだけど、両者には明確な違いがある。
それは濃さの違いで、ホリエモンの方は薄めたカルピスで、森博嗣の方は原液。あるいは具体か抽象かの違いで、ホリエモンの方はその通りに実行できるようなシンプル内容で、森博嗣の方は概念的なので「すぐ実行」みたいにはいかず、いったん自分で咀嚼する必要がある。はたまた既知か未知の違いで、ホリエモンの方は既知情報で、森博嗣の方は未知情報(というか自分になかった考え方)。
いや、そんなことより「筆者みたいになりたいかどうか」の度合いの違いか。ボクは出無精で独りが好きだから、仲間と一緒に世界中飛び回ってるホリエモンよりも、ひっそりと(?)森で暮らしてる森博嗣の方に憧れるから、必然得ようとするものが多い、みたいな。
いずれにせよ両者は優劣とかではなく、特徴の違いってだけ。
ただひとつ言えるのは、感想を書くのはホリエモンの方が圧倒的に楽ちんだということ。要するに1冊から得られる内容が少ない。それは薄めてあるから当然で、そういった本を量産して売り捌いているホリエモンはさすがビジネスの人だな、と思うばかり。一方で森博嗣も、
他のメディアもいつでもどこでも摂取できる時代になり、しかも安価で膨大な蓄積の中から選ぶことができる。できるだけ効率良くインプットしたい。「読みやすさ」が歓迎されるのは時代の必然かもしれない。作り手は、これに応える必要がある、と考えた。
位置:921
と書いているように、「読みやすさ」の需要があることは認識していて、それを小説に適応させているのはこれまでの作品を追っていればわかるけど、本書には適応しているのかな?どうなんだろ?
そうか、これまでなんとなく「気づきが少ない=読みやすい」みたいに考えていたから森博嗣の本は「読みにくい」に該当すると思ってたけど、「気づきが多いこと」と「読みやすいこと」は別軸だから両立できることで、森博嗣の本は両立してるのか。そうだよ、実際読んでて難解なとこなんかひとつもなかったじゃん>自分
ひょっとしたら、こういう「読みやすいけど気づきが多い本」のことを読書カロリーの高い本って呼ぶのかも?1冊から得られるエネルギー(気づき)が多い、みたいな。
余談:これ、1冊1記事でいい気がしてきた
感想をブログに書いてない本が溜まっているから、1記事に数冊分の感想をまとめて書く代わりに1冊の感想を短くしよう、と思って書き始めたんだけど、普通に短い感想を1冊1記事でいいような気がしてきた。とりあえず感想渋滞してる5冊に関しては複数冊を1記事にして、それ以降は1冊1記事にしよう。
ホリエモンや森博嗣みたいなプロではないけど、一応このブログも他者に読まれるために書いているんだから、「読みやすさ」を意識しないとね。
「書きたいものを書く」と「読みたいものを書く」の間には明確な違いがあるって、ものの本にも書いてあったし。
以上、
それでは~
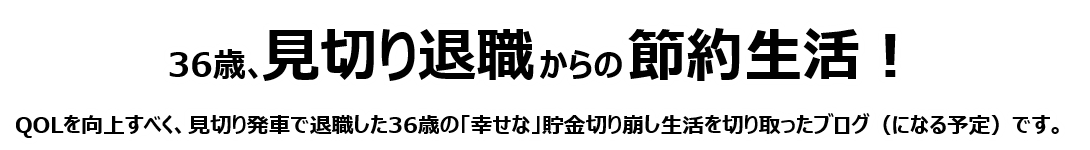
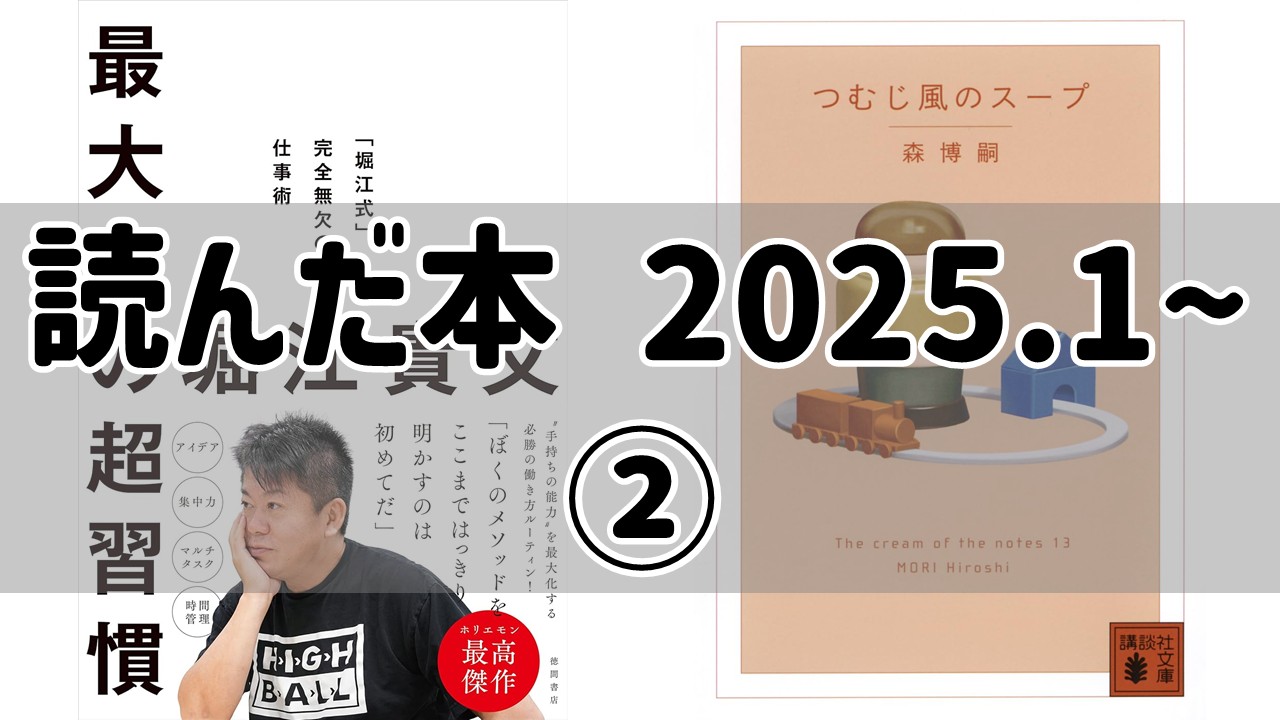


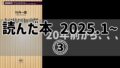
コメント