前回(2024年12月)以降に読んだ本のまとめ。
読んだ本&短文感想。
本記事の4冊はいずれもkindleで、
旅行の移動中に読んだ本。
過去の記録はこちら↓。
【橘玲】働き方2.0vs4.0 不条理な会社人生から自由になれる
電車移動中にちょこちょこ読み進めていた本。先日の上海旅行で一気に最後まで読めた。戸籍制度のグダグダっぷりが興味深かった。
「日本の働き方がおかしい」原因となる様々な非合理的な制度が挙げられているけど、この非合理っていうのは、文化や伝統っていう、「当時はそれが当たり前だったかもしれないけど今では時代遅れになっている価値観」を引きずっていることが原因なんだな、と。
で、本来なら時代に合わせて制度を根本から変えればいいんだけど、それが変更が面倒くさくて(あるいは文化や伝統が邪魔して)、付け焼き刃的な変更を繰り返した結果、非合理な制度が続いているのが今。なお、根本的な変更ができない理由には、「付け焼き刃的な変更による歪みから生じた利権」を失いたくない勢力が、躍起になって制度の正常化を妨げようとしているっていうのもある。
このように長年の歪みがたまって今にも壊れそうになってるっていうのが現状かと(まるで巨大地震のように)。っていうか多分、地震と同様、いつの時代にも「今にも壊れるぞ」って警鐘を鳴らしている人がいたんじゃないかな?それでも今までハリボテ制度で何とかなってしまっているという負の成功体験(実績)があるから、悪化の一途を辿りつつも、今から10年後、20年後、30年後も「今にも壊れるぞ」とか言いつつ、どうにかなっちゃっているのかもしれない(地震と違って物理現象じゃないからね)。破滅に漸近こそするけど決して到達しない、みたいな。
ただ、「資本主義の崩壊」みたいな全世界規模の話であれば、それでどうにかなるかもしれないけど、本書のテーマである「働き方」に関しては、諸外国との比較によって明確な差(優劣?合理非合理?)が可視化されてしまっている分、一揆とか革命的な動きが起こりやすいと思うから、資本主義が崩壊するよりは全然先に壊れると思う。
じゃあ悪化の一途をたどるしかないのかというと、一応の光明?もあるにはあって、時代に即さない制度下での働き方に端を発する格差問題は欧米が先行しているので、日本はそこからフィードバックを得て適切に対処すればよい、とのこと。政治家や官僚がこの大きなアドバンテージを活かせるかどうかはわからないけど、少なくとも個人では対処可能、と。
で、個人で具体的にどうすればいいかについては、他の橘玲本と同様、「これだ!」ってことは書かれてなくて、「自分の能力を高めておけ」「自分が活きる環境を選べ」とか抽象的な内容だった気がする。いや、これらは橘玲の別の本の結論だったかも?いずれにせよ、具体的なことが書かれていない理由(書かれていたとしても忘れてしまう理由)は、万人に共通する対策が無いから(あるいは結論に至る前段の制度の矛盾が強烈過ぎて相対的に印象が薄れるから)であり、安直に「〇〇すればよい!」と断定する自己啓発本より余程信頼できる。
日本「少子高齢化問題は我々が先行して問題の洗い出しをしておくので、格差問題の問題については海外さん、よろしくお願いします(ただし活かせるとは限らない)」
【森博嗣】読書の価値
5年以上ぶりの再読。読んで衝撃を受けた。
それは
- ボクが自分で考えたと思っていた内容が、そのまま本書に書かれていたこと
- その内容の一部については解答まで書かれていたのに、そこには自力で至れなかった(思い出せなかった?)こと
の2点。
これは
- 本書の内容を忘れて車輪の再発明をしただけなのか?
- 「本書から得た知見」ということだけを忘れて、自分で考え出したものにしてしまったのか?(無意識にパクったのか?)
どっちなんだろう?
どっちだとしても、第三者的視点からはボクが既読本の内容を自身の案としてブログに書いていたことになる。このケースでは他者への影響がほぼゼロなのでいいけれど、これが論文とかだったら確実に剽窃。怖すぎる。
まぁいくらボクでも、好き勝手書き散らかせるブログと第三者ありきで書く論文を同列にはしないだろうけど。。。
そして、「本書から得た知見」ということだけを忘れていた場合(無意識なパクリの場合)、問題提起部分は無意識に自分で思いついたことにした(パクった)にもかかわらず、その解答は思い出せなかった(自力で至れなかった)っていうのがまた滑稽で草。
どうせなら解答部分まで無意識で思い出せ(パクれ)よ、と
衝撃その1
ちなみに車輪の再発明の一例は以下。
本書からの抜粋↓。
(横溝)正史についても、なんというのか、舞台装置のデコレーションが滑稽に見えてしまう。あまりにも、非現実的だ。僕は、もうそんな日本を知らない世代なのだ。これが、もし海外ものの翻訳だとしたら読めたかもしれない。日本だとわかっているから、噓っぽく感じてしまうのだろう。
同様のことは、海外ドラマと日本のドラマでもいえる。海外ドラマは、もともと知らない世界だから、「そんなものなのか」と許容できる。日本のドラマでは、同じレベルであっても、「ありえない」作り物に見えてしまうのだ。
位置:No.453 ()内はボクの補足
ボクが過去に自分の考えとして書いた部分の抜粋↓。
小説なら文字媒体になっていることでリアルから距離を置けるけど、実写だとリアルがそのまま映るから、全部が学芸会みたいに感じてしまう。
中略
国外の実写作品でも同様のことが言えるけど、ボクは外国におけるリアリティを知らないので、仮にネイティブな人からしたら違和感が凄いとしても「こういうもんなんだな」と違和感なく見ることができる。
【本の感想】リアルとヴァーチャル【何故エリーズは語らなかったのか?】
これ、ボク的には全く同じことを言ってるので怖すぎる。いつものごとく自己正当化するなら、「自覚できただけマシ」ってことくらいかな。実際、人間の考えることなんて大抵どこかの誰かが先んじて考えたことなんだからあまり気にすることはないのかもしれないけど、ボクは森博嗣の本のファンで、その内容と同じ事についてそれが起きたっていうのがね。。。
他にも何個かありそう
衝撃その2
次は「問題に対する解答も書かれていたのに、それは全く覚えていなかったこと」について。
ボクは「本の感想に文句が多くなること」が問題だと思っていて、それについてはこの辺の記事とかをはじめとして何度も書いている↓。
で、それに対する解答が本書に書かれていて、曰く
外れという本は滅多にない。百冊に一冊もない。読むだけ無駄だったという本はない、といっても良いと思っている。
この本を読んで自分の意見や知識が塗り変えられることがあれば、と願っている。影響を受けたいという気持ちで読む。どんなものも素直に受け入れたい、と思って読む。
たとえば、間違っていると思った情報や意見であっても、そういったものの存在を知ることは有意義だ。また、間違っていたものから、なんらかの教訓や、新しい発想が生まれることも少なくない。どんなものでも、刺激になるし、きっかけになる。であれば、その出会いに感謝するべきだろう。結果的に、自分が得をする、恵まれるのだから。
嫌いなものは読まない、という姿勢を貫いていると、結局は損をすることになるだろう。つまらないな、と感じても、とりあえず最後まで読む努力をする。そのうえでやはりどうしてもつまらない場合は、次から同様の本には慎重に、という教訓になる。同様の本というのは、同じ作者、同じようなジャンル、同じようなタイトル、あるいは似たキャッチコピィの本などである。
位置:866, 872, 888, 896(太字、下線で強調したのはボク)
とのこと。
要は「得られるものにフォーカスせよ」ってことだと理解した。「そんなこと頭ではわかってるんだよ」「実践できないから困ってるんだよ」って思う自分がいるけど、それについては本書を読んだことでたぶん解決できる。なぜなら、ボクは良くも悪くも森博嗣作品の信者なので、教祖が仰ることなら盲目的に信じて実行できるから。この教え(得られるものにフォーカスせよ)については都合よく妄信(実行)させてもらおうと思う。
ってことで今後本に対して文句を書きそうになったら、本書を読んだ体験を思い出そう。
これ以降は本に対する文句が少なくなると思う。
たぶんね
【森博嗣】お金の減らし方
これも5年以上前に読んだ本の再読。
まずタイトルに森博嗣らしさを感じる。このタイトルの言わんとするところは、「お金がその効果を発揮するのは、お金と『価値』を交換するときなので、重要なのは『価値』の方。だからお金を増やすことよりも、いかに上手に『価値』と交換するか、即ちお金の減らし方が重要」ということだと理解した。
なので大切なのはお金を稼ぐことよりも、自分の価値(=自分が何に満足するか)を早いうちから把握すること。言い換えれば、やりたいことを見つけること。そうすれば必要以上に稼ぐ必要が無くなり、仕事に余計な時間や精神力を費やさずに済む。
そう考えると、「やりたいことが無い」っていう状態はよろしくない。なぜなら他者の価値観に流されがちだから。広告に踊らされるのはこういう人たち。
ただ、やりたいことの探し方っていうのは人によって異なるから、「こうすればよい」的な解答は存在しない。敢えて言うなら、外界(≒ネット)を遮断して他人の価値観を自分の中から消すことから始めてはどうか?くらいが万人に共通するであろう助言。
以上のようなことがあらゆる角度から抽象的に書かれている。抽象的な分、そのまま自分に適用できるわけではないけど、だからこそ応用して他のことにも適用できる。森博嗣の本はこの辺の突き放し方?が絶妙で、ものすごく読者に寄り添って滅茶苦茶具体的な例で示す本(たいてい裏に情報商材やコミュニティ勧誘がついてくる)よりもむしろ親切で信頼できると感じている。
ボクのお金の減らし方
以上のことをボクの生活に照らし合わせてみる。
ボクは「自分が何に満足するか」に早いうち(っていっても30代だけど)に気付けたおかげで、平均より早く退職することができたんだと思っている。
ボクが満足するのは、「やりたくないこと(=会社勤め)をしない状態である」こと。これは一般的な「やりたいこと」とは違うかもしれないけど、そこが個人的にファインプレーだと思っている。この応用のメリットは、能動的にやりたいことが無いんだから、お金と交換したい「価値」が最低限であるということ。だから資産が少なくても会社を辞めて「やりたいこと」が実現できているんだな、と。
逆に言えば、この考え方に満足できないなら、それは「やりたいことがある」ってことになるから、それはそれでOKってこと。って感じでこの考え方は自分にやりたいことがあるかどうかのセンサーとしても働くんじゃないかな?やりたいことを見つけるフローチャートの一歩目、みたいな。
今懸念しているのは、この「会社勤めしてなくて満足」という幸福感がいつまで続くのか、ということ。これは退職直後からの懸念点。とりあえず丸3年は維持できているけど、人間は「幸せだろうが不幸せだろうが”今”が基準になりがち」っていう特性があるから、いずれ会社勤めしていない状態へのありがたみが無くなってしまい、その時に再度「やりたいことが無い病」を患ってしまう可能性がある。なのでその時に備えて今から方々に種を蒔いておきたい、、、と思うこと早3年。特に何もしてないんだな、これが(笑)
あと、お金の減らし方とはズレるけど、上述の「外界(≒ネット)を遮断して他人の価値観を自分の中から消すこと」っていうのは、ボクにとっては旅行が該当する(これについては多くの人にとってもそうなんじゃないかと想像)。先日の上海旅行でも、SIMカードは買ったけど暇つぶしにネットに繋ぐようなことはせずに(そもそも暇なんかない)、目の前の景色や文化に集中できたので自分の思考を整理するいい機会になった。「家庭持ちの先輩との会話」という外界要素もあったと言えばあったけど、それはそれで自分を見つめ直すいい刺激だったと捉えている。
以下、本書を象徴すると思った文章を抜粋。
ものを買う、つまりお金を減らすことは、自分が得をするための行為だ、ということになる。その行為に及ぶときに頭の中で想像するのは、自分の気持ちである。他者がどう思うのかなんて、難しい問題ではない。
位置:411
自分の願望が、他者の関与、他者の評価だ、という点に、根本的な無理がある
位置:1777
あまりにも、周囲の空気に流されて生きてきたので、みんなと同じことが、自分がしたいことだ、欲しいものだ、と勘違いしてしまったままになっている。つまり、欲求の感覚が麻痺してしまい、好きなものを探すセンサが働かなくなっている状態といえる。これは、病気といえば病気だろう、と僕は思う。
位置2101
心が洗われるなぁ(しみじみ)。
【森博嗣】ジャイロモノレール
またまた5年以上前に読んだ本の再読。
「趣味(というか個人研究のテーマ)を持つことが人生に与える影響は大きいよ」っていうことが、ジャイロモノレールという一度途絶えた技術を復活させた著者の活動を例に書かれている(逆かも)。戦前?の特許の、あえてわかりにくく書かれている部分を読み解いていくのとか、やってるとすごい楽しいんだろうな、と思う。
当然、著者が読み解いた原理の解説が説明されていて、そこは理系知識がない人でも(たぶん)理解できるような文章で書かれていて面白かった。個人的にはジャイロモノレールという縁遠い乗り物の原理より、その前段で説明されていた「コマがなぜ倒れないのか」「自転車がなぜ倒れないのか」の説明の方が身近で頭に入ってきやすかった。コマは先端を針みたいに尖らせると逆に不安定になるのね。いずれも「ジャイロ効果」の応用
当たり前だけど、本書では「面白いからあなたも途絶えた技術を復活させましょう」と言っているわけではなく、「自分しか取り組まないような個人研究と呼べるようなものに着手するのが人生における楽しさですよ」と言っている(とボクは理解した)。自分だけの研究テーマがあるような人は絶えずそれに頭を使うからボケにくい、というようなことも書いてあり、これについては自分の周囲を観察した結果とも一致する気がしている。
そして、そんな人生の楽しみ(とボケ防止)が現時点でない人は、それを「探す」ということをしがちだけど、そうではなく、面白そうと感じたものにいろいろ手を出しているうちに勝手に「見つかる」ものとのこと。この辺りは著者の「自分探しと楽しさについて」とか「面白いとは何か?面白く生きるには?」とか他の著書にも書かれていた気がするけど、よく覚えていない。
一つ思ったのが、今(といっても本書が発行されたのは7年前だけど)は「やりたいこと探し」に対する需要がすごくあるんだろうな、ということ。なぜなら、著者は依頼されなければ本は書かないらしいにもかかわらず、似たようなテーマの本が複数あるから。で、その「やりたいこと探し」ブームは、時代の流れ的な側面ももちろんあるのだろうけど、自己啓発書とかライフハックとかそっち系が金儲けのために煽った結果の、言わば作られた流行という側面もあるんじゃないかな、なんて妄想した。
4冊の共通点
本記事に挙げた4冊の共通点は、読者に対して「〇〇するといいよ」という助言内容がいずれも抽象的であること。繰り返しになるけど、そうなるのは解答が人それぞれなんだから当たり前で、むしろ人それぞれなことに対して「〇〇しさえすればOK!」と言い放つ本が無責任なだけなんだけど。ただ、簡潔に断定する方が人気が出るのはXやYoutubeを見れば明らかだからなぁ。。。
この4冊みたいに得るものが多すぎる本に対しては、どうしても得たものを整理しようという意識が働くためか、感想というより自分の理解の要約的な文章になってしまう。まぁ何を書いてもいいのがブログの良い所だから、気にしないことにしよう。
そもそも誰も読まないしね
以上、
それでは~
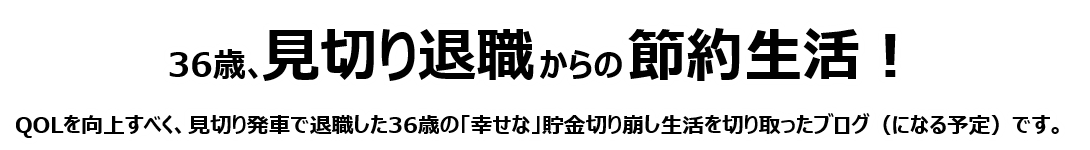
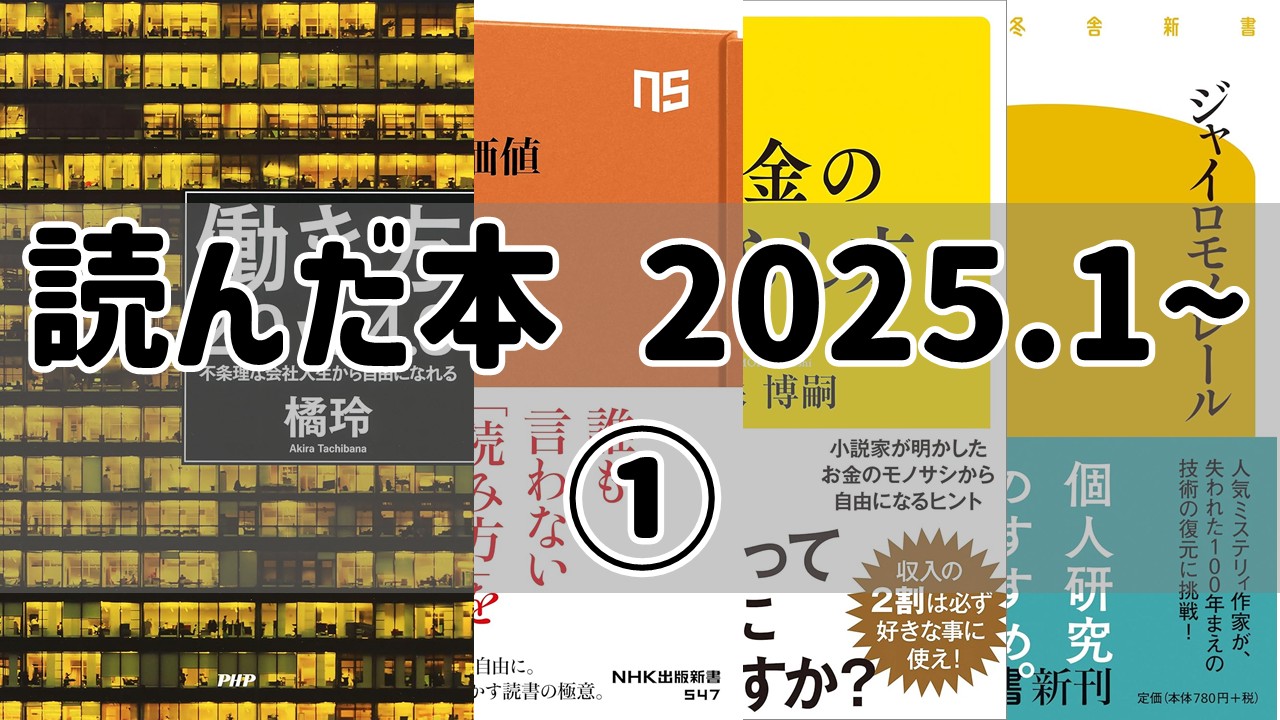




コメント