2025年1月~3月に読んだ本。
あと1冊。
過去の記録はこちら↓。
概要
- 1章:「若者の読書離れが嘘」であることを統計データで提示(タイトル回収)
- 2章:若者の読む本に共通する3つのニーズと、それらを実現しやすい4つの型を紹介
- 3章:具体例をカテゴリやジャンルごとに説明
- 4章:まとめと提言
という構成。
タイトルになってる「読書離れ」に関しては、
- 日本人の読書傾向は長らくほとんど変わっていない
- ネットやスマホの影響で若者の読書率や読書時間が著しく減少しているという傾向は見られない
というのが結論。
ではなぜ「若者の読書離れ」という嘘が事実かのように語られるのか?については、
- 実際に本離れが起きていた時代の印象に引きずられているため
- 一部情報の切り取りによりメディアが騒ぐため
- 若者が「大人が若者に読んで欲しい本」を読むようになったわけではないため
といった理由が挙げられている。
構成からもわかるように、タイトルにある「読書離れ」云々よりも、サブタイトルの「中高生はどのくらい、どんな本を読んでいるのか」と、それに伴う提言の方がメイン(だと思う)。
やっぱりタイトルは本質よりもキャッチーさを優先するんだな~
自分の「当たり前」を押しつけない、ということ
「若者の読書離れは進んでないのに、大人の思い込みで進んだことになっている。大人が若者に本を勧めるにせよ、若者の実態が理解できてなければ、ただの押しつけである」みたいなことが書いてあって、これが本書で一番印象的だった。
ここでいう「大人」とは、本が大好きでしょうがない人たちのことで、そんな彼らが平均的な子供たちに対して自分たちの水準の読書を押しつけている、という構図。
この歪みが「若者の読書離れという嘘」を生み出す一番の原因、ひいては出版業界衰退の原因なのかな、と(森博嗣も複数の本に似たようなこと書いてた記憶)。
これは別に出版業界に限った話ではなく、ぱっと思いつく所で言うと、「霞が関の人たちが作るルールは高学歴者の読解力を想定されているので多くの一般人には理解不能だから、結果として役所の担当者の負担が増えている」っていうやつ(体験談)。
つまり、
「平均から逸脱した人」が、自分たちのやり方を「普通」とみなしてしまっていることで、「平均的な人」の現実との間に理解のギャップや負担が生じている
って感じか。
この手の問題に関しては、もうどうしようもないんだろうな。
企業とかなら代わりがいくらでもあるから自然淘汰が起きて上手いこと回っていくだろうけど、政治に関してはどうなんだろう?
よくわかんないけど、ボクが生きてる間はツギハギ付け焼刃になりつつも、なんとか体裁は維持していてほしいな(無責任)。
「二兎追うものは一兎も得ず」を行ったラノベ
次に印象的だったのはラノベの衰退について。
「ラノベを売る側が対象年齢を中高生1本に絞らず、スケベ心から対象年齢を(読者の成長に合わせて)高年齢化してしまった結果、高年齢側は”なろう系”に、低年齢側は”児童書”に読者を乗っ取られた」っていう話が、なろう系のざまぁ展開みたいでちょっと面白かった。ラノベの役どころが噛ませ犬っていうのが高得点(笑)
ここからも無理やり教訓っぽいことを捻りだすと、
- ターゲットは明確にして、ズラすな
- ターゲットから外れつつある「今の客」の声に踊らされるな
って感じ?
子供向けの作品を作ってる人たちは、「自分は面白いと思わないけど、子供はコレが面白いと思うはず」という意識で作品を作ってるのかな?それとも「作者本人が子供の感性を持ってるから、自分が面白いと思うものが子供にウケる」という状態なのかな?
前者は職人、後者は天職っていうんだろうな。
ボクの読書歴
以下自分語り。
本書の3章で、「若者が実際にどんな本を読んでいるのか」がカテゴリ、ジャンルごとに示されているんだけど、「児童書→ノベライズ→ラノベ→一般文芸」っていう紹介の流れがボクの読書歴に概ね沿っていて、人間(日本人?)としての読書傾向ってあるんだな、と。
具体的なボクの読書歴は、小学校から順に「おうさまシリーズ」「ずっこけ3人組」「エルマーの冒険」「ゴクドーくん」「ノベライズ(金田一、ワンピース、スパイラル)」「バトルロワイヤル」「涼宮ハルヒ」「フルメタルパニック」「ミステリー全般」「西尾維新」「西澤保彦」「辻村深月」「森博嗣」と通ってきて、その後就職して本を読まなくなって、しばらく(数年)してからネットで「なろう系」って感じ。
在職時代は「なろう系」を、退職してからは「実用書」を読むようになるっていう読書傾向の変化については、別記事に書いた記憶↓。
これ、バーナム効果ってやつでは?
書いてて思ったんだけど、本書で説明されてるジャンルとかカテゴリって概ね有名どころを網羅している(気がする)ので、ある程度本を読んできた人であれば「自分に当てはまってる!」って思うのはある意味当然なのでは?(笑)
占い師が当たり障りないことしか言ってないのに「あたかも自分が言い当てました」っていうやつとある意味同じなのかも(バーナム効果だったかな?)。
余談:あのシリーズの続刊、どうなってる?
それと余談だけど、「ゴクドーくんシリーズ」「チョーモンインシリーズ(西澤保彦)」の2つって、著者が公式に「絶対完結させる」って言ってた記憶があるんだけど、ちゃんと終わってるのかな?
ついでに「涼宮ハルヒ」も、あれ全然続刊が出なくてボクは卒業しちゃったんだけど、完結したの?
調べてみたら、それぞれ
- ゴクドーくん:「作者の中村は続きが書けなくなったと述べている」(by Wikipedia)
- チョーモンイン:2006年で発表は中断。既刊絶版。イラストの水玉螢之丞は死去 (by Wikipedia)
- 涼宮ハルヒ:2020年末に9年半ぶりの新刊発売(by Wikipedia)
とのこと。
なんていうか、はい。。。
信用貯金のやりくり
ここまで書いて、ふと「作家と政治家の共通点として(別にこれら職業に限った話ではないだろうけど)「発言内容に責任をとらなくて良い」っていうのがあるな」と思った。
責任はとらなくてもいいけど、代わりにどちらも客に対して不誠実な対応(作家の場合、「出す」って言って出さないとか、刊行期間空きすぎとか)をすると信用が失われ、浅めのファンから徐々に離れていくよな、と。
ただ、コアなファンは不誠実な対応をしてもついてくるし、彼らがお金をくれるなら別に知ったこっちゃない、っていう理屈が成り立ちそう(政治家はたぶんこの理屈だよね)。
たとえばゴクドー君の作者に関しては「ラノベ→エッセイ」と畑を変えることで浅いファンを切り離して新規ファンを獲得してるし、涼宮ハルヒの作者は「もう一生分稼いだ」から、最早ファンを気にしなくても良くなった、とか?そしてチョーモンインに関しては、作者は当時から複数シリーズ(作品)を並行して書いてたから、シリーズごとに浅いファンがいる状態なので、ひとシリーズ(のファン)切っても食べていけるのだと想像。
そう考えると彼らは信用貯金のやりくりが上手なんだな、と。
生存者バイアスなだけかもだけど
それと同時に、ハンターハンターを書き続けてくれている冨樫先生には頭が上がらないし足を向けて寝られないな、と(一応涼宮ハルヒの作家もこの枠になるのか?)。
まとめ
- 『「若者の読書離れ」というウソ』を読んだ
- このような嘘が発生する原因のひとつには、「平均から外れた読書家」の基準が、いつの間にか「普通の人にも当てはまるべきもの」として扱われてしまっている、という構造がある(と思った)
- ラノベの衰退の話が「典型的なビジネスの失敗例」みたいで面白かった
- 一生分稼いだ(と思われる)のにH×Hを書き続けてくれる冨樫先生、ありがとうございます
以上、
それでは~
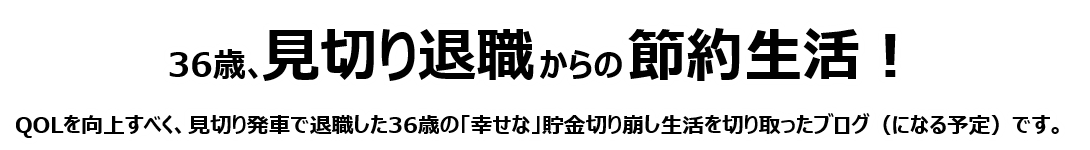
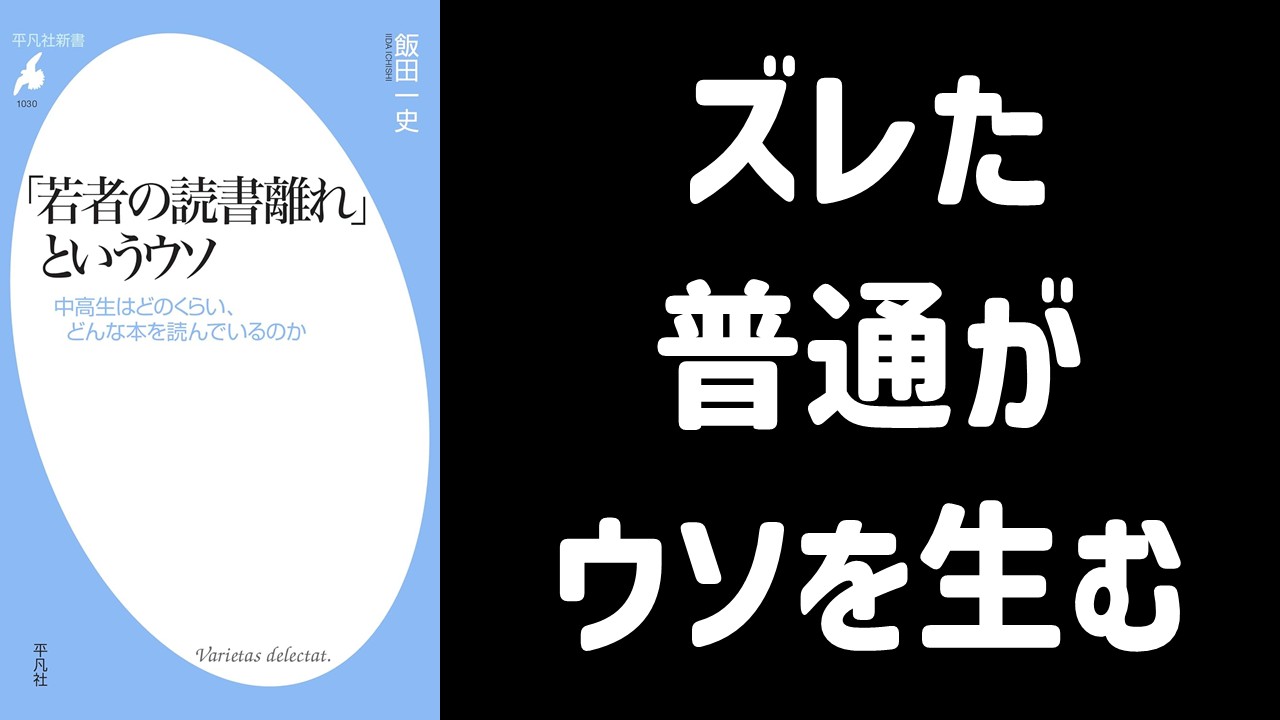



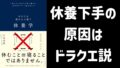
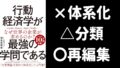
コメント