2025年1月~3月に読んだ本。
これでおしまい。
今更だけど
本の感想記事を
読んだ時期で区切ることに
意味はないので、
今後からは時期で区切るのはやめよう。
過去の記録はこちら↓。
概要
内容としては他の行動経済学の本と同じで、〇〇効果とか〇〇理論みたいな名前の付いた(=統計的に傾向が認められた)現象について色々書かれている。
他著との違いは、「行動経済学を体系化した初の本」であることらしい。
本書の言う体系化とは、「非合理な意思決定に影響を与える要素を『認知のクセ』『状況』『感情』の三つに分け、行動経済学の各理論をこの三つに分類したこと」。
そして、「この体系化により、これまでバラバラだった主要理論が有機的につながる」らしい。
感想:”体系化”は典型的タイトル詐欺要素だと思った
ボクの感想を一言で言うと以下の通り。
本書の言う「体系化」は販促のためのキャッチコピーで、甘い判定でもせいぜい「カテゴライズ」だと思う。
例えば学生が行動経済学のテストに合格するために「現象とその名称」を覚える際には、本書の言う「体系化」が役に立つとは思う。
でもボクにとっては「そういう現象がある」ということを知るのが重要で、名前なんか覚える必要はない(名前を知りたければ都度調べればいい)。
なのでボクが本書をラベリングするなら、「本書は『ファスト教養』に特化した行動経済学の本」と言えるかな。
以下、感想。
というか妄想。
「体系化」とはいったい・・・うごごご!!
本書は、序章をまるまる使って、
- これまでの行動経済学の本は体系化されていない
- 本書が初の体系化された本だ
ということが書かれている。
その一方で、
- 歴史の浅い行動経済学に対して、まだ学問的な体系化はできない
- 本書はビジネスパーソンのリクエストに応えた体系化だ
という弱気?な記述も見受けられる。
そこにチグハグな印象を受けたんだけど、そこからちょっと妄想してみた。
編集者と著者の温度差
前提として、本書の著者は
- 日本人として数少ない行動経済学の博士課程取得者であり、
- 日本との接点が少ない
らしい。
このことを踏まえつつ、本文中の記述に
- (著者は)日本と疎遠
- 出版社から連絡が来た
- (著者の)つたない日本語
- 表紙やタイトルは自分で決めなかった
といったような表現が出てくることから、以下のような妄想ができる。
行動経済学の本が売れることに気づいた出版社の人が、それっぽい権威を持った日本人を探していたら、著者に行き当たった。
↓
編集者は他著との差別化要素として体系化を売りにしたいことを著者に伝えた
↓
でも学者としての著者は「そんなの無理」と回答。
↓
編集者は「そこをどうにか」と食い下がる。
↓
最終的に妥協の結果として、それっぽく情報を整理したことを無理やり「ビジネスマン向けの体系化」と言い張るという着地点を見出した。
↓
ただ、当然著者は本書が体系化ではないことを重々承知しているので、本文中に「あくまでもビジネスパーソン向けの体系化だよ」「覚えやすいように情報を整理しただけだよ」というフォローを入れた
↓
それを出版社が大々的に「行動経済学初の体系化本」と謳って売り出した。
更に妄想を重ねると、出版社は著者のフォローの部分をカットしたかったまであるんじゃないかな?
我ながら流石に妄想が過ぎるけど、一応話の筋としては通っていると思う。
よくある話なんだろうな
実際のところ、こういうのはよくある話で、「医者(特に美容系)がお金目当てに消費者を騙すようなことを言う」みたいな話はよく聞こえてくる。
この例では医者も売ることに対して積極的だけど、本書はその亜種で、「売るために(極論)嘘をつきたい編集者 vs 正確に書きたい(誤解を与える表現をしたくない)著者」なのかな?と妄想した次第。
もっと簡潔に言えば、「商売人vs学者」の構図。
「だから何だ」って話ではあるけど、ボクにとってはそのくらい読んでいて上述のチグハグさが目立ったということ。
無職・無所属ゆえの「一人エコーチェンバー化」に要注意
最近こういう妄想をしがちなんだけど、ひょっとしたらこれは危険な兆候なのかもしれない。
他人と言葉のキャッチボールをする機会が少ないから、一人エコーチェンバーに陥ってしまって、妄想を真実だと思い込んじゃう系の人に自分がなりやしないかという危険を感じている。
これは例えばChatGPTに相手してもらえば解消されるのか?というとそう単純な話でもないはず。
「50%の確率で反論してください」みたいな設定にしておかないと、ChatGPTは単なる全肯定マシーンになるので、エコーチェンバーに拍車がかかるだけだから。
まぁこうやって「危ない」って自分で書いているうちは、自覚があるってことだからたぶん大丈夫でしょ(楽観)。
まとめ
- 「行動経済学が最強の学問である」を読んだ
- 紹介されている内容は、他の行動経済学の本と変わらない
- 覚えやすいように並べたこと(本書曰く「体系化」)が本書の特徴
- 「正確に書きたい著者 vs 売りたい出版社」の構図を妄想した
- 「妄想」と自覚できてるうちは問題ないはず
行動経済学の本を読んだのに、感想に行動経済学の内容が出てこなかった。
これはボクの中で行動経済学が飽和したってことだから、しばらくは行動経済学の本は読まなくていいかな。
以上、
それでは~
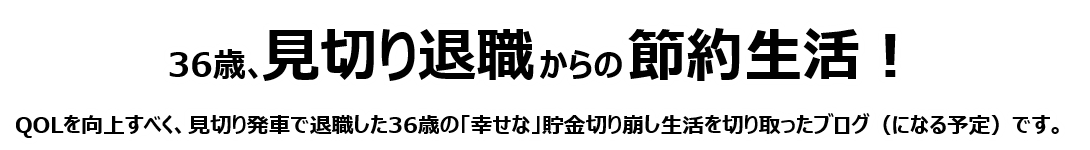
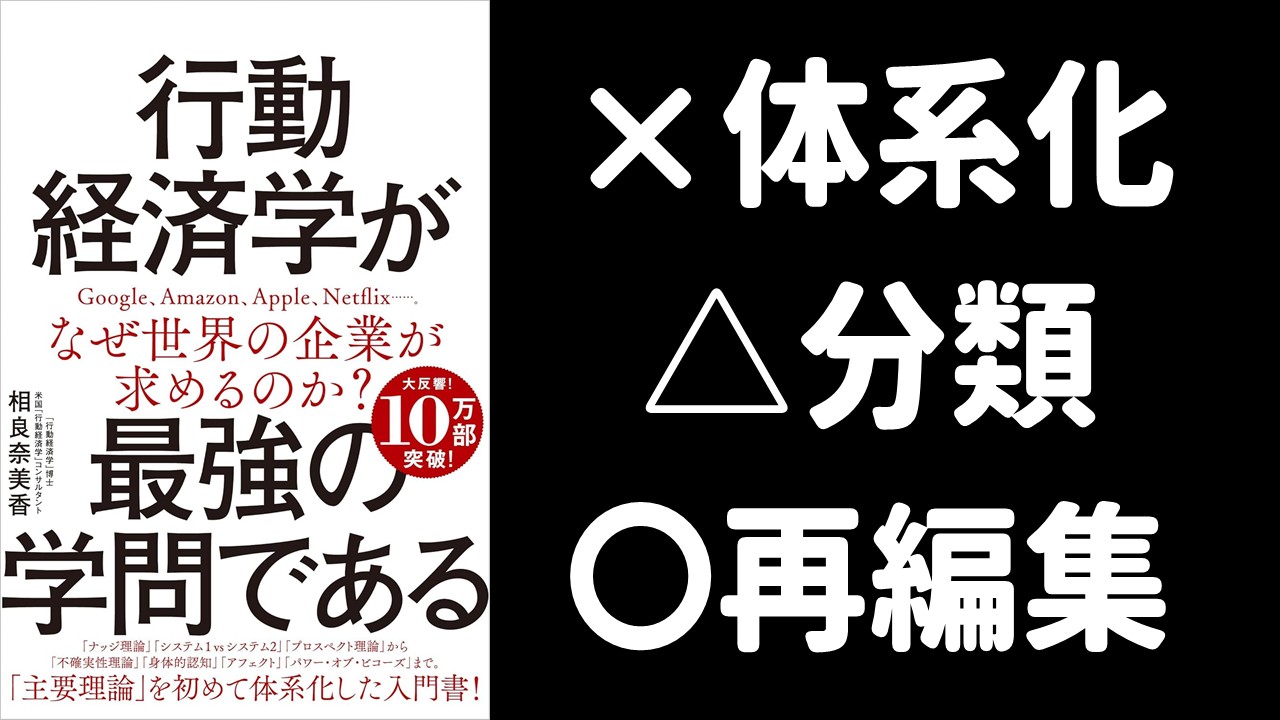


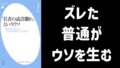
コメント